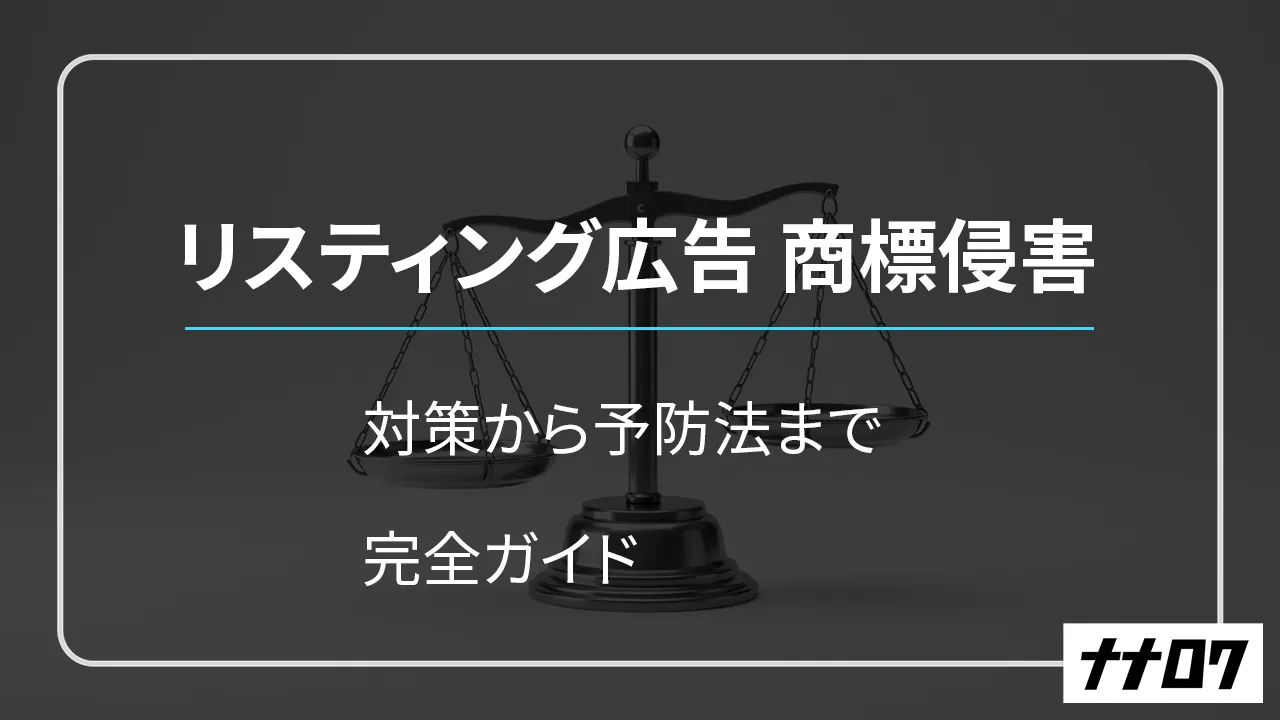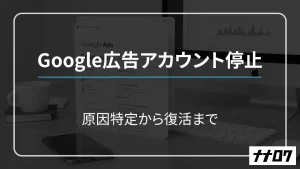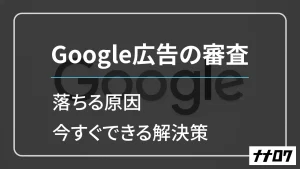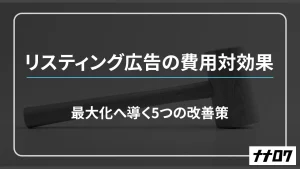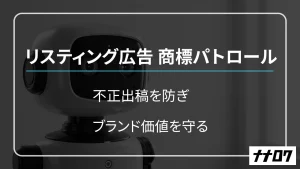リスティング広告で商標を無断使用され、お困りではありませんか。これはブランド価値を損なう、深刻な問題です。
しかし、正しい知識を持てば、適切に対処できます。この記事では、商標侵害の定義から具体的な対策までを解説します。
- リスティング広告の商標侵害は、ブランド価値や広告費に悪影響を与えます。
- 侵害には「キーワードでの利用」と、より深刻な「広告文での利用」があります。
- 広告文に使われた場合は、GoogleやYahoo!など媒体への申し立てが有効です。
- 一方でキーワード利用には、競合他社への直接交渉で対応するのが基本です。
- 意図せず加害者にならないための、具体的な予防策についても解説しています。
そもそもリスティング広告の商標侵害とは?

リスティング広告の商標侵害は、登録商標を権利者の許可なく使用することです。
そのため、ビジネスに大きな影響を与えます。具体的には、自社のブランド名が、他社の広告で使われるケースがほとんどです。このような行為は、顧客の混乱を招く可能性があります。
リスティング広告で起こる2種類の商標トラブル
商標トラブルは、主に2つのパターンに分類されます。
1つ目は、競合が「キーワード」として商標を使用するケースです。
そして2つ目は、競合が「広告文」に商標を表示するケースです。
これらは似ているようで、リスクの大きさが全く異なります。そのため、それぞれに応じた対処法が求められます。
なぜ商標権の侵害がビジネスリスクになるのか?

商標権の侵害は、単に不快なだけではありません。なぜなら、具体的なビジネス上の損害につながるからです。
放置することは、自社の首を絞めることになりかねません。したがって、迅速な対応が不可欠です。ここでは3つのリスクを解説します。
ブランド価値の毀損と顧客の混乱
自社ブランド名で検索した顧客が、競合の広告を目にするとどうなるでしょうか。
顧客は、提携企業だと誤認するかもしれません。また、ブランドイメージが悪化する恐れもあります。
結果として、顧客の信頼を失うことにも繋がります。
クリック単価の高騰と広告費の浪費
競合が自社の商標キーワードで入札すると、オークションの競争が激化します。
その結果、自社の広告のクリック単価(CPC)が高騰します。つまり、本来不要な広告費を支払うことになるのです。
これは、広告予算の深刻な浪費と言えるでしょう。
本来得られるはずだった機会の損失
競合の広告に顧客が流れ、自社サイトへのアクセスが減少します。
これは、見込み顧客を奪われることを意味します。
つまり、商標侵害は売上や問い合わせの機会損失に直結するのです。したがって、この問題は決して軽視できません。
【ケース別】これは商標権侵害?法的リスクと媒体ポリシーの境界線

リスティング広告の商標利用は、すべてが違法とは限りません。
法的解釈と、GoogleやYahoo!などの広告媒体が定めるポリシーは異なります。
そこで、ケース別にその境界線を詳しく見ていきましょう。この違いを理解することが、適切な対応の第一歩です。
ケース1:競合の商標を「キーワード」として使用する場合
競合の商標名を、広告の表示をトリガーするキーワードとして設定する行為です。これは、多くの企業が実施しているかもしれません。
しかし、そこには複雑な背景が存在します。ここでは、その実態を解説します。
法的・ポリシー上の見解
現在の日本の法律では、キーワードとしての使用だけでは商標権侵害と断定されません。なぜなら、キーワードはユーザーに見えないからです。
また、GoogleやYahoo!のポリシーでも、キーワードでの商標利用は制限されていません。そのため、媒体への申し立ても基本的には不可能です。
事実上はグレー?紳士協定が求められる背景
法的に問題ないとしても、倫理的な課題は残ります。
同業他社間で商標キーワードを使い合うと、業界全体のCPCが高騰します。その結果、誰も得をしない消耗戦に陥ります。だからこそ、多くの業界では暗黙の紳士協定が存在するのです。
ケース2:競合の商標を「広告文」に表示する場合
一方で、競合の登録商標を自社の広告文に表示する行為は全く異なります。
これは、ユーザーに誤解を与える可能性が非常に高いです。そのため、問題視されるケースがほとんどです。具体的にどのようなリスクがあるのかを見ていきましょう。
明確な商標権侵害と見なされる可能性
広告文での商標使用は、商標法で定められた「商標の使用」に該当する可能性が高いです。
特に、顧客が提供元を誤認するような使い方は、明確な侵害行為と判断されます。実際に、このようなケースは媒体ポリシーでも原則禁止されています。
ユーザーの誤認を招く「なりすまし」行為とは
例えば、公式サイトであるかのように見せかける広告文は悪質です。これは、ユーザーを騙す「なりすまし」行為に他なりません。
このような広告は、ブランドの信頼性を著しく損ないます。したがって、発見次第、即座に対応すべきです。
【防御編】自社の商標が他社広告で使われた時の全手順
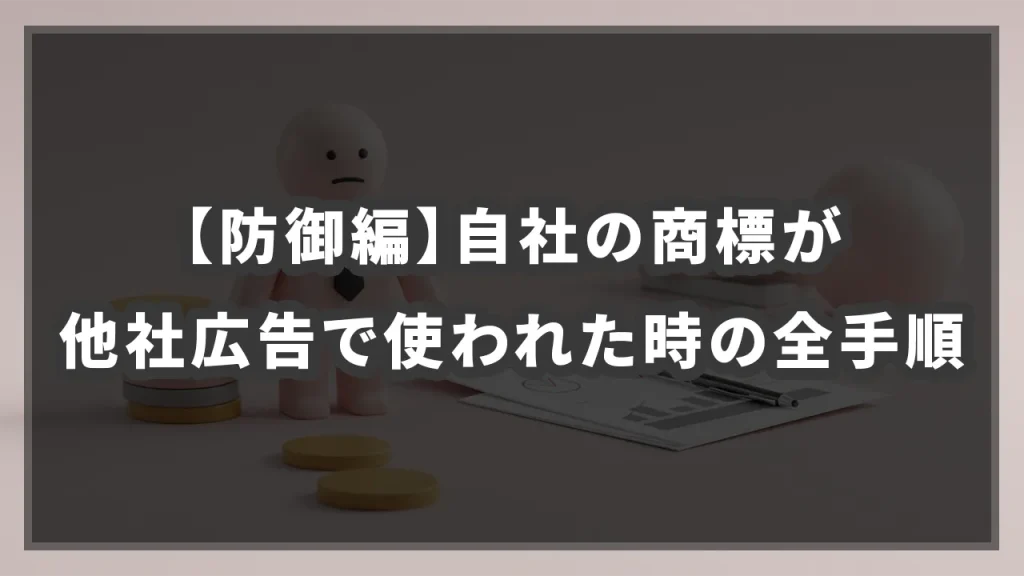
もし自社の商標が不正利用された場合、冷静かつ迅速な行動が求められます。しかし、焦って行動すると、かえって事態を悪化させることもあります。
そこで、具体的な対処手順を解説します。この通りに進めれば、問題解決に繋がります。
まず確認すべきこと:キーワード利用か、広告文利用か
最初に行うべきは、状況の正確な把握です。
問題の広告は、商標を「キーワード」として使っているだけでしょうか。それとも、「広告文」にまで表示されているでしょうか。
前述の通り、この2つは対処法が全く異なります。まずはスクリーンショットなどで証拠を保全しましょう。
広告文で無断使用された場合の対処法:媒体への申し立てが有効
広告文に商標が使われている場合、最も効果的なのは広告媒体への申し立てです。
Google広告、Yahoo!広告ともに、商標権侵害を報告するための専用フォームを用意しています。この手続きによって、広告の掲載を停止させることが可能です。
Google広告への申し立て手順
Google広告での商標侵害には、所定の手続きが必要です。具体的には、必要な情報を揃え、専用フォームから申請します。ここでは、申し立てをスムーズに進めるためのポイントを解説します。事前に準備を整えることが重要です。
申し立てができる人
申し立ては、商標権者またはその代理人のみが行えます。具体的には、企業の法務担当者や、依頼を受けた弁護士・弁理士などが該当します。関連会社や取引先は申し立てできません。そのため、権利関係を明確にしておく必要があります。
事前に準備が必要なもの
申請には、商標の登録情報(登録番号など)が必須です。また、侵害している広告の具体的な情報も必要になります。例えば、広告主の会社名や表示URL、広告文のスクリーンショットなどです。これらを事前にまとめておくと、手続きが円滑に進みます。
申請フォームと注意点:自社アカウントの許諾を忘れずに
Google広告のヘルプページから申請フォームにアクセスします。ここで注意すべき点があります。それは、自社の広告アカウントで商標の使用を許諾する設定です。これを忘れると、自社の広告まで停止する恐れがあります。必ず設定を確認してください。
Yahoo!広告への申し立て手順
Yahoo!広告の場合も、基本的な流れはGoogle広告と同様です。しかし、いくつか異なる点も存在します。ここでは、Yahoo!広告に特化した申し立て手順と注意点を解説します。プラットフォームごとの違いを理解しておきましょう。
申し立てができる人
Yahoo!広告でも、申し立てができるのは商標権者またはその代理人に限られます。これはGoogle広告と共通のルールです。正当な権利を持たない第三者からの申請は受理されません。したがって、立場を明確にすることが求められます。
事前に準備が必要なもの
申し立てには、商標登録原簿の写し(PDFなど)が必要です。加えて、侵害の事実を証明する資料も求められます。具体的には、広告が表示された検索結果ページのスクリーンショットなどです。これらの客観的な証拠が、申し立ての信憑性を高めます。
申請フォームと注意点
Yahoo!広告の公式サイトにある専用フォームから申請します。申請時には、侵害内容を具体的かつ簡潔に記載することがポイントです。感情的な表現は避け、事実を淡々と伝えましょう。また、自社での利用について問題ない旨を書き添えることも重要です。
キーワードで無断使用された場合の対処法:競合への直接交渉
前述の通り、キーワードでの商標使用は媒体への申し立てが困難です。そのため、競合他社へ直接連絡し、出稿の停止を依頼する方法が現実的です。
もちろん、これは簡単なことではありません。だからこそ、丁寧かつ戦略的なアプローチが求められます。
交渉を円滑に進める依頼メールの3つのポイント
直接交渉を成功させるには、メールの書き方が非常に重要です。まず、高圧的な態度は絶対に避けましょう。
次に、商標キーワードでの出稿が双方に不利益である点を論理的に説明します。
最後に、代替案を示すなど、協力的な姿勢を見せることがポイントです。
そのまま使える!出稿停止を依頼するメール例文
下記例文を適宜修正を加えて利用することも可能です。
件名:【株式会社〇〇】リスティング広告におけるキーワード使用に関するお願い
株式会社△△
ご担当者様
突然のご連絡失礼いたします。
株式会社〇〇の担当、〇〇と申します。
貴社がリスティング広告を出稿されている中で、
弊社の登録商標である「弊社サービス名」をキーワードとして
ご使用されていることを確認いたしました。
この状況は、ユーザーの混乱を招く可能性があると考えております。
また、業界全体のクリック単価高騰の一因となり、
双方にとって広告費用の増大に繋がる懸念がございます。
つきましては、大変恐縮ではございますが、
当該キーワードでの出稿を停止していただけないでしょうか。
何卒、ご理解ご協力いただけますと幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。
今後とも、良好な関係を築いていければと存じます。
---
株式会社〇〇
部署名:〇〇
担当者名:〇〇 〇〇
連絡先:03-1234-5678
---【予防編】意図せず商標権を侵害しないための対策
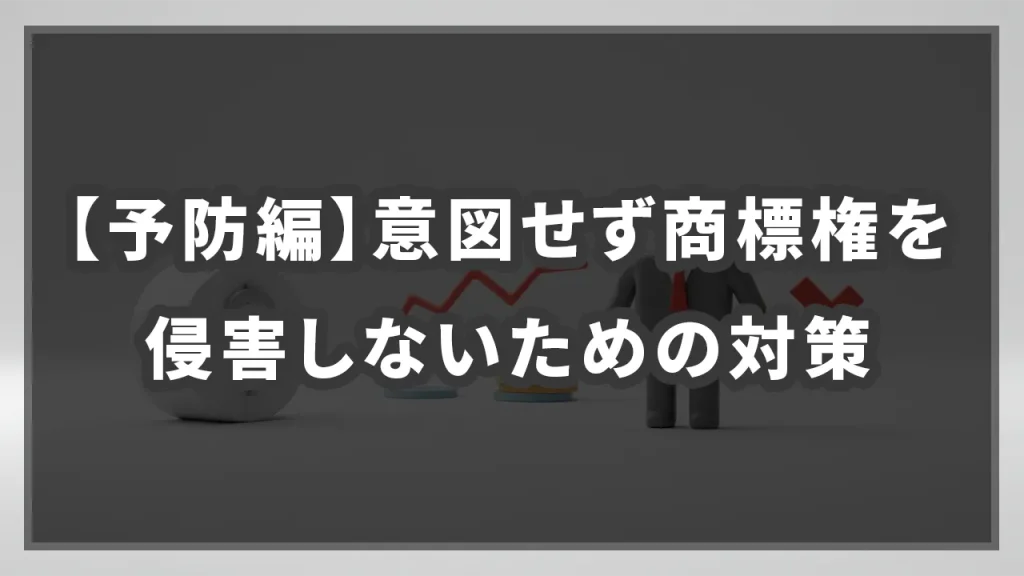
これまでは被害者側の視点で解説してきました。
しかし、意図せず加害者になってしまうリスクも存在します。そこで、自社が商標権を侵害しないための予防策も重要です。
知らぬ間にトラブルに巻き込まれないよう、日頃から対策を講じておきましょう。
「部分一致」の思わぬ落とし穴と回避策
広告媒体のキーワード設定「部分一致」は便利な機能です。しかし、意図しないキーワードで広告が表示される原因にもなります。例えば、他社の商標名を含んだ検索語句に、自社広告が表示されるかもしれません。これは、除外キーワード設定で他社の商標を登録することで防げます。
定期的な出稿キーワードのモニタリング体制を構築する
実際にどの検索語句で広告が表示されているか、定期的に確認する体制が不可欠です。
広告媒体の管理画面にある「検索語句レポート」を活用しましょう。そして、意図しない語句があれば、すぐさま除外設定に追加します。この地道な作業が、将来のリスクを減らします。
商標監視ツールの活用も選択肢に
手動での監視には限界があります。特に、多くのキーワードを管理している場合は大変です。そこで、商標監視ツールを利用するのも一つの手です。
これらのツールは、自社商標での競合出稿を自動で検知してくれます。結果として、監視業務の効率化が可能になります。
まとめ
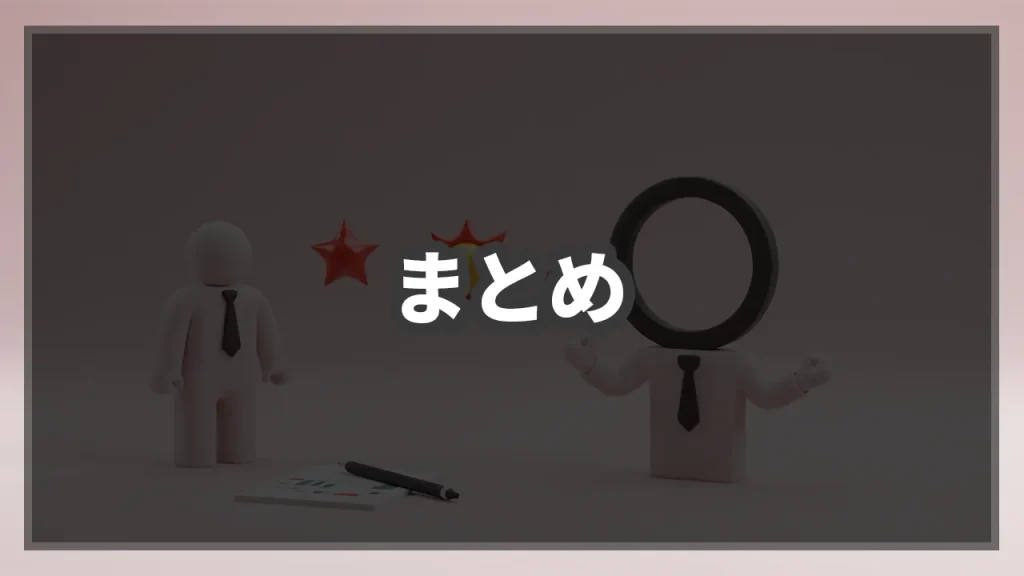
リスティング広告における商標侵害は、複雑な問題です。
しかし、広告文での使用には媒体への申し立てが有効です。
また、キーワードでの使用には、丁寧な直接交渉が求められます。さらに、意図せず加害者にならないための予防策も忘れてはいけません。
しかし、もし対策が思うように進まない場合や、不正アフィリエイトの特定などが必要になった際には、弊社にご相談ください。

- 夜間の商標リスティング出稿や、IPアドレスを変えての不正出稿を対策したい。
- 商標パトロールをツールで行い本業に割く時間を増やしたい。
- 商標のCPC高騰を抑えたい。
fugatoではこれらのお悩みにお応えすることができます。
よくある質問
Q. 申し立てをしてから広告が停止されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 一概には言えませんが、通常は数営業日から2週間程度かかることが多いです。媒体側の調査状況や、申し立て内容の複雑さによって期間は変動します。そのため、余裕を持った対応を心がけましょう。
Q. 競合への交渉に応じてもらえない場合はどうすればよいですか?
A. 交渉が不調に終わった場合、次の手段として弁護士や弁理士に相談することをお勧めします。専門家を通じて警告書を送付するなど、法的なアプローチを検討する段階になります。ただし、費用も発生するため慎重な判断が必要です。
Q. どこまでが「類似商標」として侵害の対象になりますか?
A. 類似商標の判断は、非常に専門的な知識を要します。具体的には、商標の見た目(外観)、読み方(称呼)、意味(観念)などを総合的に考慮して判断されます。自己判断は難しいため、不安な場合は特許庁のウェブサイトで確認するか、弁理士などの専門家にご相談ください。